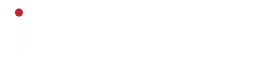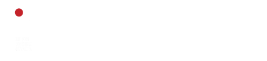武蔵関教室では定期的に教室内報を作成しています。数年前から各教師が持ち回りで「私が子供だった頃」というタイトルでエッセイ(作文)を書き掲載していました。
このページではその一部をにっきょうのHPでも掲示し皆様にも読んでいただこうと思いました。拙い文章ではありますが、それぞれの教師にも少年時代があり、それぞれの想い出があるわけです。塾生にもそんな教師の一面を少しだけでもわかってもらえるとうれしいなと思い、書き綴ってもらいました。
「あの日、あの時・・・」豊田(教室長)
瀬戸内の穏やかな海に面した地方都市で他の多くの先生方と同じように昭和そのものの少年時代を過ごした私が経験したあの日、あの時とは。
貧乏という言葉が普通に使われ、戦争で足を切断した傷痍軍人らしき人が物乞いをする光景に接していたわけなので、同じ昭和でも「三丁目のタ日」にかなり近い時代でした。漫画とテレビで育った世代でもあります。当時の大人が浸画を有害だとみなす風潮は、今の大人がゲームを敵視する以上のものがありましたが、今やマンガもゲームも日本を代表する文化となっていることを思うと感無量です。
それはさておき、我々の世代が今の子供たちより幸福だったのは間違いないでしょう。確かに物質的にはまだまだ貧しく、トヨタ自動車のデザインもとてもダサくて、アメリカの消費生活が憧れの的であった時代ではありましたが、将来のことをなんにも思い煩う必要がなかったことが今との一番の差でしょうね。インターネットもテレビの衛星中継もない情報量の少なさのおかげで、大人たちがキューバ危機に世界の破滅を感じていたなどということも知らずにすみました。
スポーツも勉強も出来て先生方の覚えめでたき優秀な姉と、10代の宇多田ひかるのような口髭を生やした生意気な妹に囲まれ、男一人、爺さん、婆さんにも可愛がられてすくすくと育ちました。確かに、あの日、あの時までは。
小学校の3年になったばかりでしょうか、父親の勤めていた会社の社宅には幼児から大学生まで多くの子供たちがいました。その中の誰かに誘われて社宅の隣にある警察遺場で行われていた剣道の練習に通うようになりました。私以外はみんな年上で、中学生、高校生のお兄ちゃん達と楽しく通っていました。そのうち、練習帰りにお好み焼きやによっていくのが習わしとなり、50円だか100円だかのお金が必要になってきました。何十年も前の記憶なのではっきりしませんが、最初はおごってもらっていたのだと思います。当時お小遣いというのはもらってなかったか、もらっていてもごくわずかだったので、自然とあくまで自然とそんなに罪悪感もなくタンスの中の母親の財布に手が伸びていました。それが何回続いたかも思い出せませんが、剣道を始めて一年ぐらいたったときでした。ある日いつものように学校から帰ると母親が鬼のような形相で待ち構えていました。金を取ったことを確認するやいなや有無を言わさず私の腕をひっつかんで外に連れ出し、警察に連れて行くというのです。あまりのなりゆきに気が動転し、ピーピー泣きわめき、「もうしません。もうしません。」と訴えたのですが、母親はなにも答えずものすごいカで引っ張っていきました。
警察署まで来ると、さすがに観念してしくしく涙を流していると、中からとても優しそうなオジサンが出てきました。泣いている私の肩に手をまわし、諭すようにやさしく しゃべってくれたことを思い出します。そのあと、母親と何を話したか、どのように家に帰り着いたか全く記憶にありません。ただ、あの日、あの時、なにも思い煩うことのない幸福な少年時代と確かに決別したのだと感じました。
ぼんやりとではありますが、人生にはいろいろあることを学び、私にとって忘れられない大人への一歩を踏み出した出来事でした。おそらく、同世代の友人たちの中では比較的恵まれた小学生時代を送ったY少年は中学で大きな転機を迎え、最低、最悪の高校時代へ突入しますが、その顛末はまた次回に…。
「私が小学生の頃」中田(国語科)
小学生のころは学校から帰るとすぐに遊びに行き、かくれんぼやどろけい(ドロボウとけいさつ)などをして遊んでいた。季節により遊びはいろいろあったが、その中でもソフトボールやサッカーは独自のルールを作り、日が暮れるまでやっていたな。だから小学校5年生になると学校 対抗ソフトボール大会に参加できるってのが楽しみでしょうがなかった。
背はクラスで前から3番目で体はほとんどの人に勝てなかったが、 ソフトボールは小さいころから得意だった。父親は社会人野球のピッチャー。6つ年上の長男は漫画「巨人の星」にみせられて中学では野球部のピッチャー兼セ ンター。典型的な野球一家だった。年のはなれた自分は兄と父がキャッチボールをするのについていき、それをながめながら時々シャドウピッチングをしながら 「明、やるかっ!」って言葉を待ち遠しく思っていた。投げ方についての指導は時には暗くなるまで続き、教わった投げ方のコツは翌日学校に行ってからも思い 返してはシャドウピッチングしていた。
そんな野球漬けの小学生だったが、球技は何でも好きで、家にはグローブとバットだけでなく、サッカーボールや拾ってきたバレーボールもバドミントンセットも卓球セットもあった。それでも野球とソフトボールは一番よくやった。廃校になった小学校の狭いグラウンドでのホームランは、垣根をこえてボールが人家の庭(よくほえる大きな犬がいたんだよな)かお茶畑(ここに入るとなかなか見つからない!)に入ってしまうことだった。ホームランを打った最高の気 分とその後の大人に見つからないようにボールを探しに行くスリルは今でも目に浮かぶ光景だ。
住んでいたのは学習塾なんてあるわけない静岡の山の中。同じ集落に同級生の男子は3人だけ(しかも苗字は3人とも長嶋。笑)。だから学年の枠なんかな く、上下3年くらいの幅でいつも遊んでいた。そうでなければサッカーもソフトもできないわけだしね。おかげで体格のいい上級生とも対等に戦える技術はどん どん身に付き、5年生になれたときは自信を持ってソフトボール大会に出られるぞと、期待していた。
ところが……、その年から大会はソフトボールからサッカーに変わってしまったのだ。なんなんだ~これは~とショックを受けた。ふてくされるくらいにショックを受けた。不良になってしまおうかしらんと思うほどのショックだった!
他に何の楽しみもなかった自分の小学校生活はこれで終わったとさえ思った。
でもね、本当の楽しみとサッカーの面白さを知ったのはこの後からだった。大活躍もたくさんあったんだよ。わかる人はわかるように、静岡だからね、まずサッカーありきなんだよ。でもこの辺でおしまいにしないとあと3倍は書かなくてはいけなくなるから…。では……ん? 勉強はって? 勉強は少しはしていたのかもしれないけど、思い出せないな。確か体育と音楽と、あとは算数が得意だったと思う。国語? まったく思い出せません。まあいいじゃないですか。
では、失礼します。
「ある夏の記憶」白井(算数・数学科)
あれはどういう星のめぐり合わせだったのだろう。本の虫でもない僕が、中学一年から三年まで図書委員だった。
学校の図書室の運営や読書をひろめる運動に、生徒らが自主的にかかわっていくという図書委員会で、各学年から十名ほどの男女がえらばれ、委員になるのだった。
新刊が入荷されると、紹介する記事を書かされたりしたが、僕はたまに書き、適当にさぼった。ある時は、本の整理をするフリをして、書架と書架のあいだの、紙の匂いの立ち込める通路をゆっくりめぐりながら、世界中にはこの図書室の何千倍、何万倍もの書物があって、それを書いた作家がいるのだということを、ぼんやり思っていた。
台風が接近している、ある夏の午後。
本の整理をしながら、窓に近い書架へ回り込むと、女の子が立っていた。知らない子だった。知的なひたいと銀縁のめがねが印象的な、小柄な女生徒で、一冊の本をひらき、小さな声で音読している。その声は、窓から吹きつける夏の風といっしょに、僕の耳にふわっと届いた。
「それ、どんな本ですか?」思わず、僕は訊いていた。
「奇巌城よ。怪盗アルセーヌ・ルパン全集の。もう、読んだ?」
首を横にふる僕に、彼女はほほ笑み、この本はぜったい読むべきよ、と言った。友だちに秘密にしている宝物をそっと僕にだけ教えてくれるみたいに、本の表紙を見せてくれた。
その夜、家の屋根をこれでもかと叩きつける激しい雨音をききながら、『奇巌城』を読みはじめた。やがて、この世のあらゆる音が遠ざかるのを感じ、僕は、広大な物語の森へ、連れて行かれた。