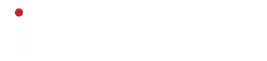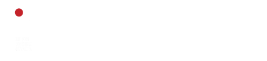「わが昭和43年、君は不二家のペコちゃんを知っているか」山口(英語科)
その日、トオル少年は朝からひとつの期待に胸をふくらませていた。日曜日だったが、パパは朝から仕事に出かけていた。出がけにパパがママに「帰りは9時頃になる」と言うのをトオルはたしかに聞いた。今夜はウルトラセブンが見られる。そう思うと夜が待ち遠しくてならなかった。先週も先々週も、チャンネルはパパに奪われてしまって、ウルトラセブンを見そこなった。しかし今夜、パパはいない。
月曜日はいつもウルトラセブンの話でもちきりになる。明日はタケシ君ともイサム君とも話ができる。みんなウルトラセブンの活躍を熱っぽく語ったが、ほんとうはアンヌ隊員の話をしたいのだった。このごろはタケシ君を中心に輪ができるようになった。タケシ君の家にカラーテレビが入ったからだった。セブンはおそい時間だからおまえたちを呼ぶことはできないが、メキシコオリンピックが始まったら見せてやってもいい、とタケシ君はじまん気に言った。まるで子分にされているみたいでいやだったけれども、カラーテレビのある家の子はえらいという事実はみとめないわけにはいかなかった。
待ちに待った夜7時、テレビはとっくに6チャンネルに合わせてある。武田製薬のCMが終わった。「セブン!セブン!セブン!」というイントロを聞くとトオルはもう胸の高まりをおさえることができなかった。カラーだったらどんなにすごいだろう。トオルはやっぱりタケシ君と仲良くしようと思った。と、そのときであった。
玄関の呼び鈴が鳴った。ママが戸を開けにいった。仕事が早く終わったというパパの声が聞こえた。トオルは目の前が真っ暗になった。パパは居間に入ってくると、テレビの前にすわっているトオルには目もくれず、チャンネルをNHKに回した。そうしてふすまを開けてとなりの部屋に着がえに行った。ニュースは今日もベトナム戦争だった。つまんないな。だまってテレビを見るパパをトオルはうらめしそうに見た。
ニュースが終わるとパパは横になって寝てしまった。パパの寝顔を見ながらトオルはパパなんかどこかに行ってしまえ!と思った。チャンネルを6に回してみたがもちろんウルトラセブンは終わっていた。ブラウン管にうつっているのはおばけのQ太郎だった。CMになるとペコちゃんが不二家のパラソルチョコレートの宣伝を流していた。
この世にペコちゃんほどおそろしい子供はいない。トオルはそう思っていた。駅の近くの不二家のお店にもペコちゃん人形があったが、トオルはなるべく近づかないようにした。ペコちゃんは子供のくせにまゆ毛をそっていたし、風もないのにいつも頭がふらふらゆれていた。(つづく)
「英語」中谷(算数・数学科)
中学生のとき、私は英語の塾に通っていた。そこは今から考えても相当ハードで、当時の私には泣きたくなるほどきつかった。問題集を4~5冊ほどつかい、そこから山のように宿題がでた。量だけならなんとかこなせたが、私を一番悩ませたのが暗記の宿題だった。中でもつらかったのは、教科書の丸暗記だった。テストは、白紙に何も見ないで教科書と同じ文章を、和訳をそえて書け、という形式だった。
小学生時代、英語を全然勉強していなくて、塾に入る前も、「ローマ字さえ書ければいいですよ。」といわれ、安心していたが、すぐに入塾したことを後悔した。覚えるまで書けといわれたが、最初は10回書いても覚えられなかった。正直、こんなことをして本当に意味があるのだろうか、と思った。だが学校のテストのときには、自分でも驚くほど、すらすらと答えが頭の中に浮かんできた。
2年、3年と学年が進むにつれ、だんだんと楽に覚えられるようになってきたが、それでも他教科の勉強ができないほどきついのには変わりなく、得点が一番取れるのは英語だったが、一番嫌いな教科も英語だった。みなさんも学校の英語のテストで思ったほど得点が取れないなと感じたら、教科書の丸暗記を試してみて下さい。
「いじめられっ子、柔道に出会う」佐藤(英語科)
「また、あいつらだ。」胸がドキドキした。北の国が一番寒くなる2月のある日の放課後のことだ。少し遠くに見える4、5人の連中が僕を待ち伏せしているのは明らかだった。月に一度か二度少し離れた町からやって来る、ひとつかふたつ年上の体の大きい連中だった。
「いやだな」
背中に冷たい水をかけられたような感覚が僕を包んでいた。今度は何をされるんだ?
小学校3年の僕はやせっぽちの弱虫だった。学校でもいじめっ子にやられっぱなしだった。やられても、やり返せない弱虫だった。6歳の頃に大きな病気をした僕は保育園にも行けず小学校に入った時はほとんど友だちもいなかった。もちろん字も書けず、計算もできない、今の子供たちからは考えられないような、間の抜けた小学生だったのである。そんな僕はまわりの腕白たちから見ればいじめる格好の標的だった。
隣町の上級生がそんな僕の噂を伝え聞いたとは思えないが、だれから見ても「いじめてください」という看板を背中にはりつけて歩いているように見えたのだろう。
「よぉ。一人でどこ行くんだよぉ?あぁ?」
一番体の小さい、けど一番くせの悪そうな奴が言った。手には安全ピンを持って針の部分を僕に向けている。
「いっしょに遊ぼうぜ。」
そう言いながら僕のアノラックの上に安全ピンをチクチク刺してくる。アノラックには綿がいっぱい詰まっているから安全ピンの針は肌までとどきはしない。それをわかった上でそんなことをするいやな奴だった。
僕はこわかった。びびっていた。当たり前だ。学校では一対一でもやられる僕が、五人の、それも体の大きな上級生の連中にからまれているのだ。泣きたくなった。でも、僕は逃げることもできずに黙っていた。
「ふん。おもしろくねぇな。そら、行けよ。」
そいつが言った。まわりにいる連中もニタニタ笑いながら僕を見ている。僕は少し早足でその場から立ち去ろうとした。ちょうどそのときだ。
「おい!」
僕は振り向いた。その瞬間、顔に何かが思い切り当たった。連中の中で一番体の大きな奴が投げたザラザラした雪玉だった。鼻に当たった痛さといじめられたという怖さのため僕は思いきり泣いてしまった。泣きながら走って家に帰った。いじめっ子のいじめになすすべもなくやられてしまう自分が情けなかった。
数日後学校でチラシが配られた。春から町の道場で柔道教室が始まるお知らせだった。僕は家に帰り、母に柔道を習ってもいいかたずねた。母は二つ返事で「いいわよ。習ってみたら」と言った。僕が生まれて初めて自分から何かを習いたいと言い出したからだ。
柔道教室の先生には接骨院を生業にしているおっさんを中心に町の豪傑がたくさん来ていた。接骨院のおっさんは大のお酒好きで稽古をつけてもらうとお酒のにおいがぷんぷんして僕らを辟易させたけど、柔道は強かった。昔から喧嘩がめっぽう強く、へっぽこ小学生の僕らをびしびし鍛えてくれた。
先生の中で一番えらい人は高校の校長をしている人だった。彼は先生達の中でただ一人黒帯ではなく紅白帯をつけた柔道六段の強者だった。なぜかはわからないけどその先生は僕を特にかわいがってくれた。先生との稽古は投げられっぱなしで畳に投げつけられるととても痛かったけど、どんどん自分が強くなっていくような気がした。先生は僕に技のはいるタイミングをとことん教えてくれた。タイミングがドンピシャ合うと柔道は体が小さくても大きな相手を投げ飛ばせることを教えてくれた。そして百回投げられる中で一回は投げさせてくれた。技が決まると僕はうれしかった。
そして柔道を習い始めてから僕の性格が大きく変わっていった。何にでも積極的に取り組めるようになり、クラスでも「ねぇ、君ってあんがいおもしろかったんだね」と言われるくらいお笑い系の男の子になっていったのである。わざわざ上級生の女の子たちが僕のギャグを聞きに教室まで出向いてきたほどだった。(そのギャグは今ではおもしろくないのであえてここには書かない)
もちろんいじめられることもなくなっていった。だって休み時間に体育館で相撲ごっこをやる時僕ら柔道少年団の連中はめっぽう強かったからだ。低学年の時僕をいつもいじめていた連中も、僕に一戦を挑みことごとく投げ飛ばされてしまったからメンツ丸つぶれだった。柔道様々!柔道グレイト!である。
そんな僕らは中学に入り柔道部を作った。顧問は担任の先生にお願いした。当時はアントニオ猪木がプロレス界のスーパースターで、僕らは新日本プロレスに熱狂していたから柔道部の練習は半分プロレスごっこだった。野球部や女子バレーの連中は僕らのことをゾウキン部と呼び、嫌っていたけど、僕らは彼らが成し遂げられなかった全道(北海道だから全道ね)大会出場を中学3年の時に果たしたのだ。ゾウキン柔道部グレイト!柔道少年団に栄光あれ!である。
亡くなる前まで、母がよく言っていた。「他人に何かを教えてもらうのが嫌いだったあんたが一番長続きしたのは柔道だったね。よかったね、柔道習ってて」
そうだな、と今でも思う。あのとき柔道に出会っていなければ僕は今でも弱虫のまま背中を丸めて道をトボトボ歩いていたかもしれないのだから。